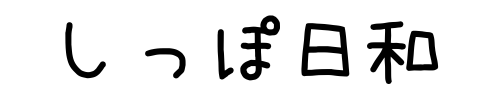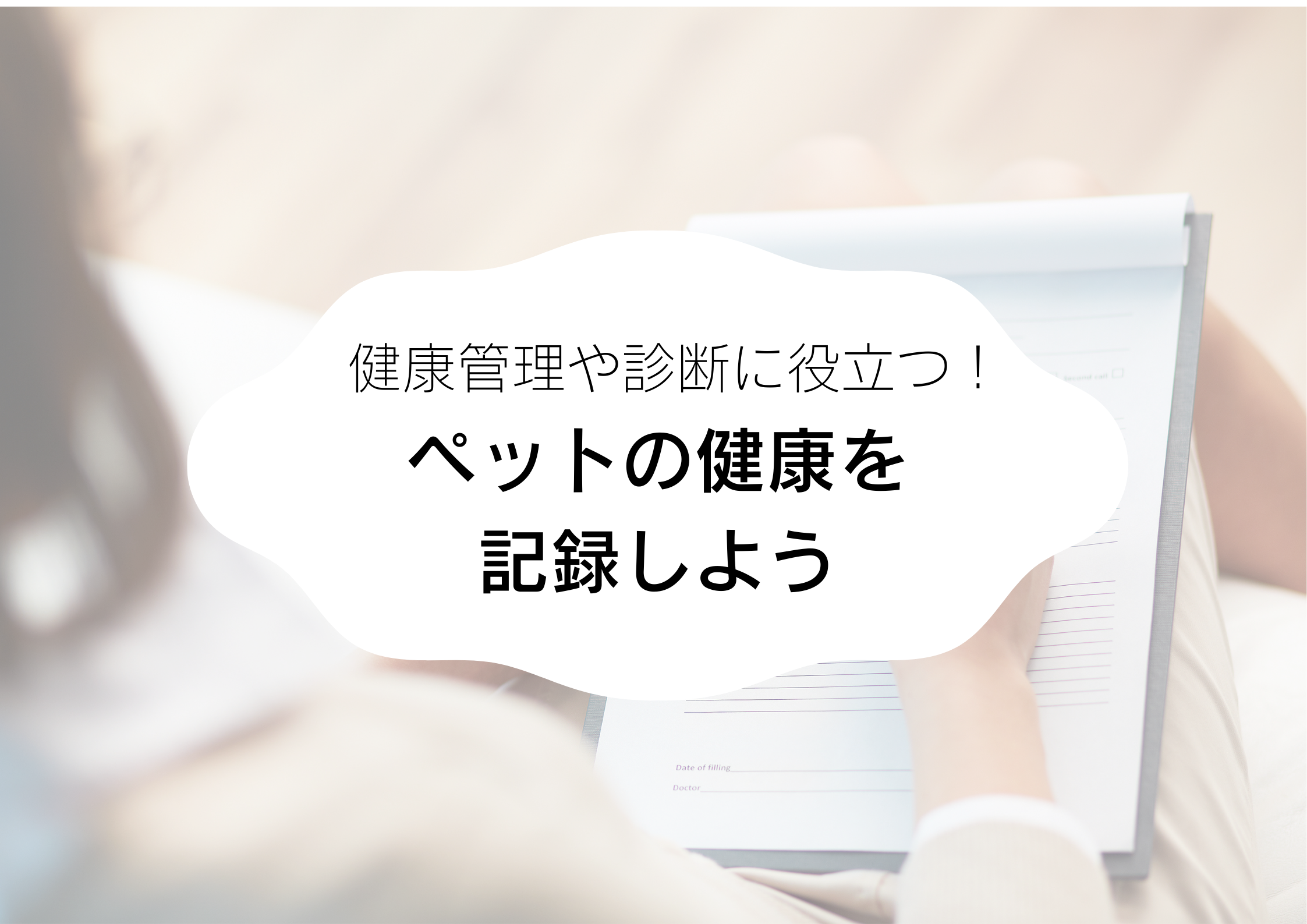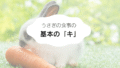病院に行く時に必ず受ける「問診」
ところで、問診はどんな役割を果たすかご存じでしょうか?
どんな症状があるか、いつ頃から症状がでたか…きっかけや期間、症状や頻度などを問診票に記入したり、お医者さんとお話をしますよね。
問診とは、罹患している可能性のある疾患を絞り込み、検査内容を決め、診断につなげる
いわば「情報収集」の時間です。
問診に加えて触診や聴診、視診を行い体からさらに多くの情報を得ます。
そして主観的な情報(問診)と客観的な情報(触診・聴診・視診)を照らし合わせて最短距離で、より正確な答えを導き出していきます。
では、動物の場合はどうでしょう? 
触診や聴診は獣医師が行うことができますが、人の言葉を話せない動物の問診では一緒に暮らす家族の話が重要な鍵になります。
その内容が詳しければ詳しいほど、情報が多いほど、獣医の助けになるだけでなく不必要な検査や処置による動物への負担を減らすこともできます。
一方で、ただ単に情報が多ければいいというわけではありません。
関連のない情報が多すぎると、必要な情報を取捨選択するために時間と労力を費やすことになり、結果的に動物の負担を増やしてしまうことになります。
つまり診療に役立つ「有益な情報」が多ければ多いほど良い、ということですね。
では”診寮に役立つ情報”とは一体なんなのでしょうか?
そのひとつが「健康記録」なのです。
今回は、記録の種類と注目したいポイントについてお話しいていきたいと思います。
記録はなぜ必要?
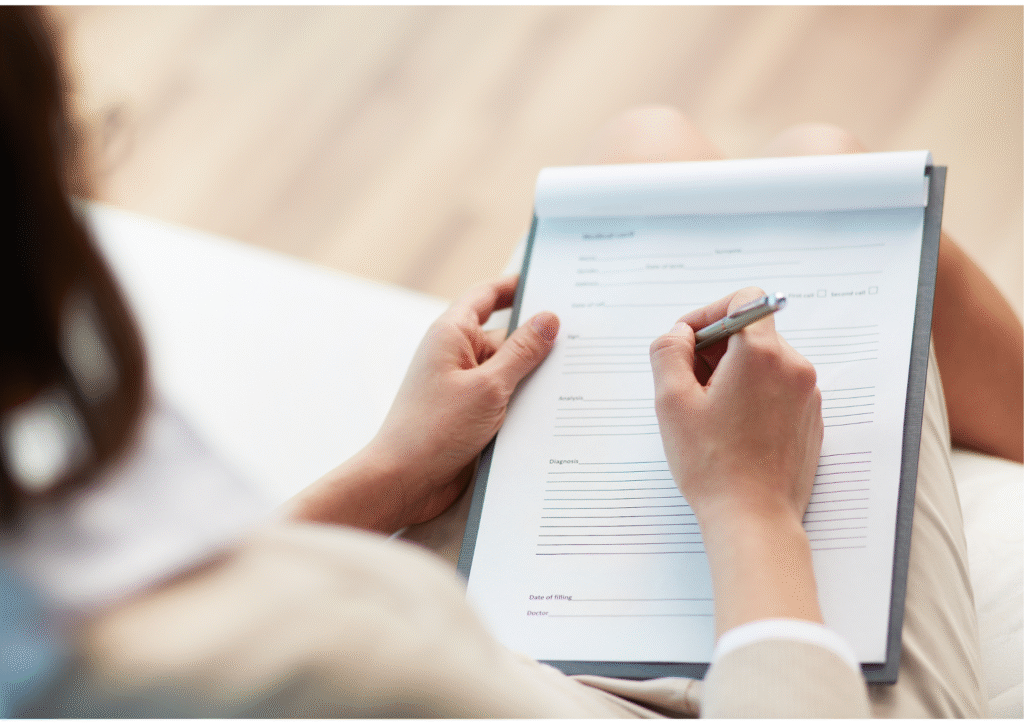
動物を病院に連れて行く時、「おかしい」と感じて動物病院に連れて行きますよね。
この「おかしい」という感覚は、普段の様子と比べて「いつもと違う」ことが根拠になっています。
そしてそれが「どう」違うのか?ということが、診察ではとても大事なポイントなのです。
例えば、”嘔吐”で来院されたとします。
- 1週間前から吐いているのか昨日から吐いているのか
- 1日1回程度なのか1日何度も吐くのか
- 食後すく吐くのか食前に吐くのか
「嘔吐する」という行動は同じでも、どのように吐いているかで考えられる可能性は方向性を全く変えます。
そこで役に立つのが「記録」なのです!
特に症状が頻繁に続いてる場合、 すべての出来事を頭の中だけで記憶しておくことはなかなか簡単ではありません。
人の記憶というのは案外あいまいで、時間が経つにつれ事実と違ってきてしまうこともしばしばです。
不安や心配する気持ちから、混乱して記憶がこんがらがってしまうこともありますよね。
記録をつけていれば
◎忘れてしまっても見返せて
◎事実が変化せずに
◎ "正確な情報" を探し出すことができ
◎前の記録と比べた変化を客観的に判断できる獣医師に正しい情報を伝えることができるだけでなく、動物の様子のちょっとした変化に気づく手がかりにもなるのです。
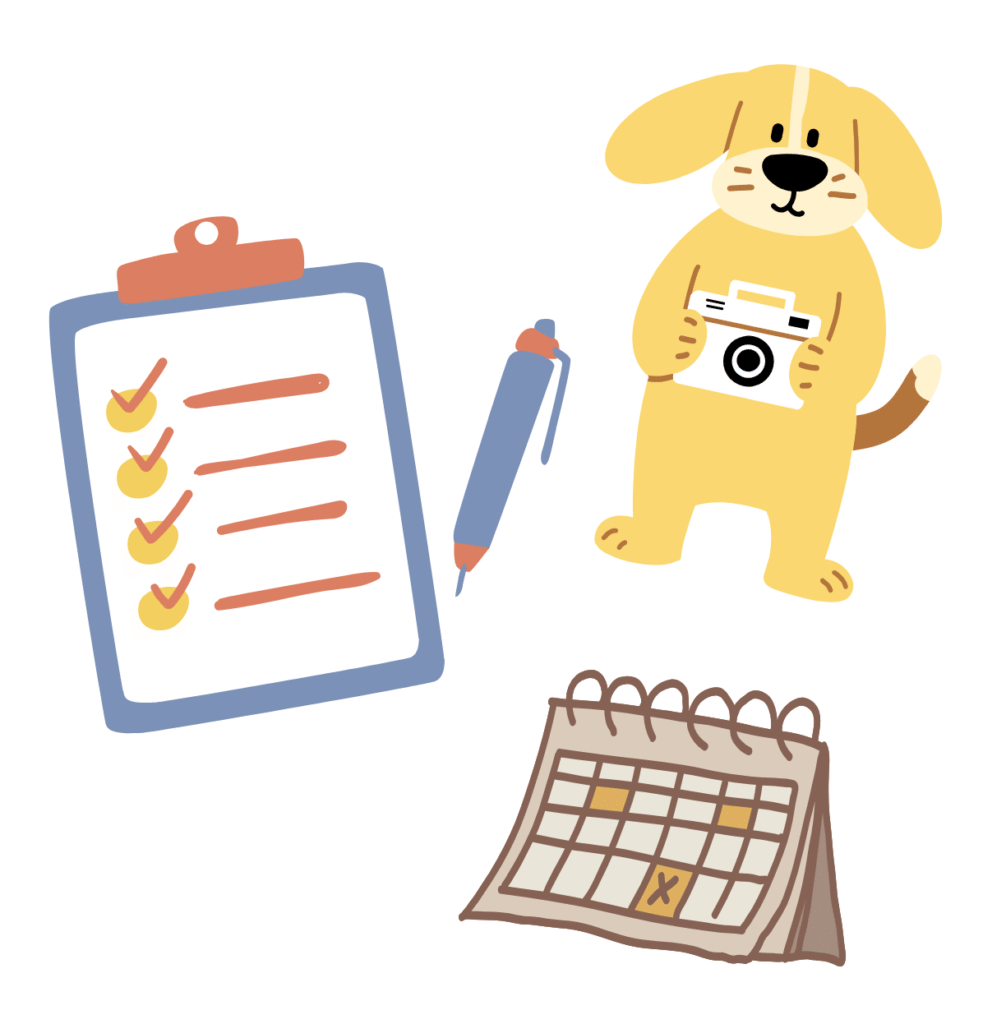
- ノートに記入する
- 携帯にメモしておく
- カレンダーに印をつける
- 写真や動画に撮っておく
など記録の媒体は人それぞれでOK!
自分がやりやすいようにオリジナルのチェック表を作って、みなさんもぜひ記録をつけることを習慣にしてみてください。
記録方法の種類と特徴
記録は継続することが大事なので、各々が継続しやすい方法で行うのが一番です。
ただし記録方法によっては向き不向きがあるので、「何を記録したいか」によって複数の記録方法をアレンジして行うのがおすすめです。
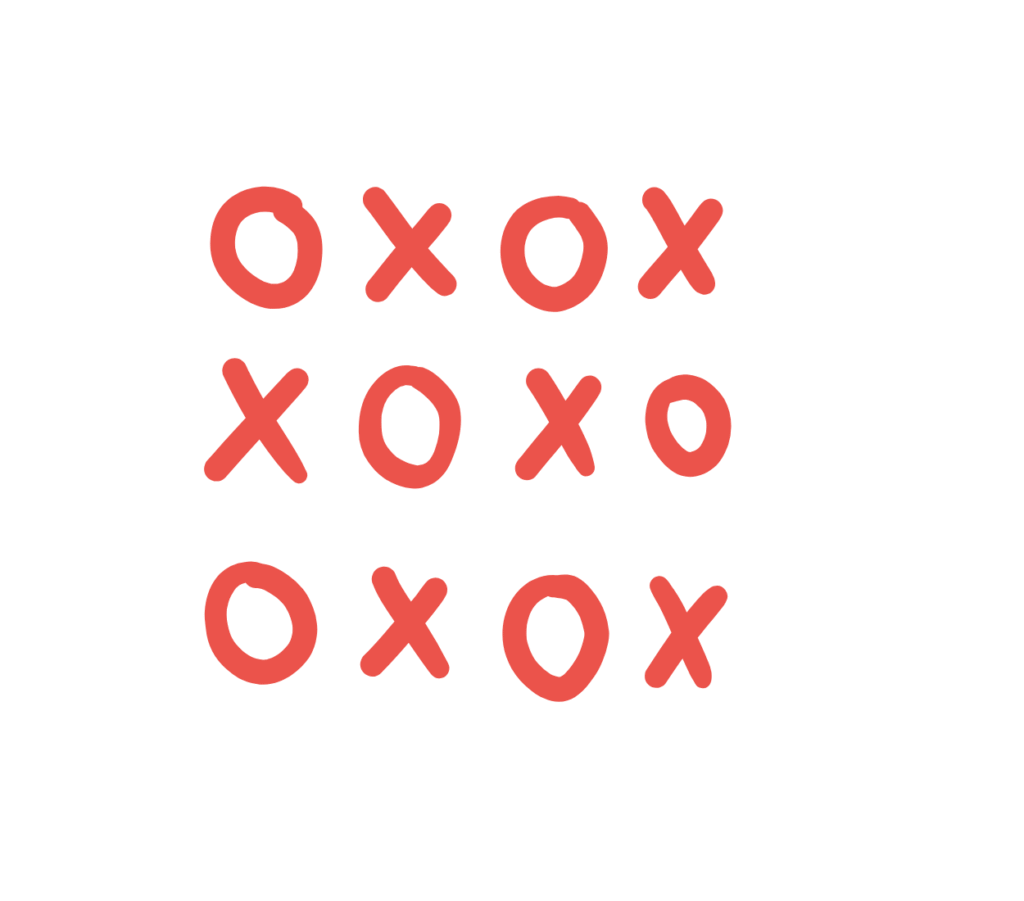
事実の有無を記録
出来事の有無や、行動や物事の「回数」「頻度」を数えるのに適している
◎得意
:排便・排尿回数、発作の有無、嘔吐の有無、できもの(腫瘤)の有無、目ヤニや鼻水の有無など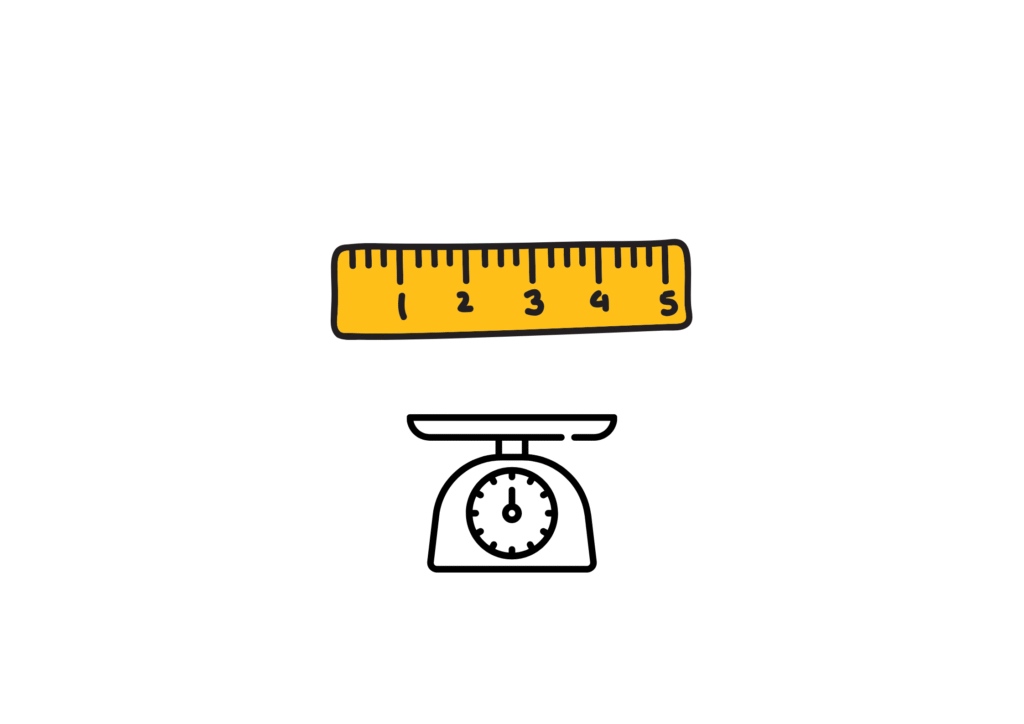
量を記録
ものの「重さ」や「長さ」などの大小や多寡、短長を測るのに適している
◎得意
:食事量(食べた量、残した量)、飲水量、尿量、便量、誤食物の量、体重など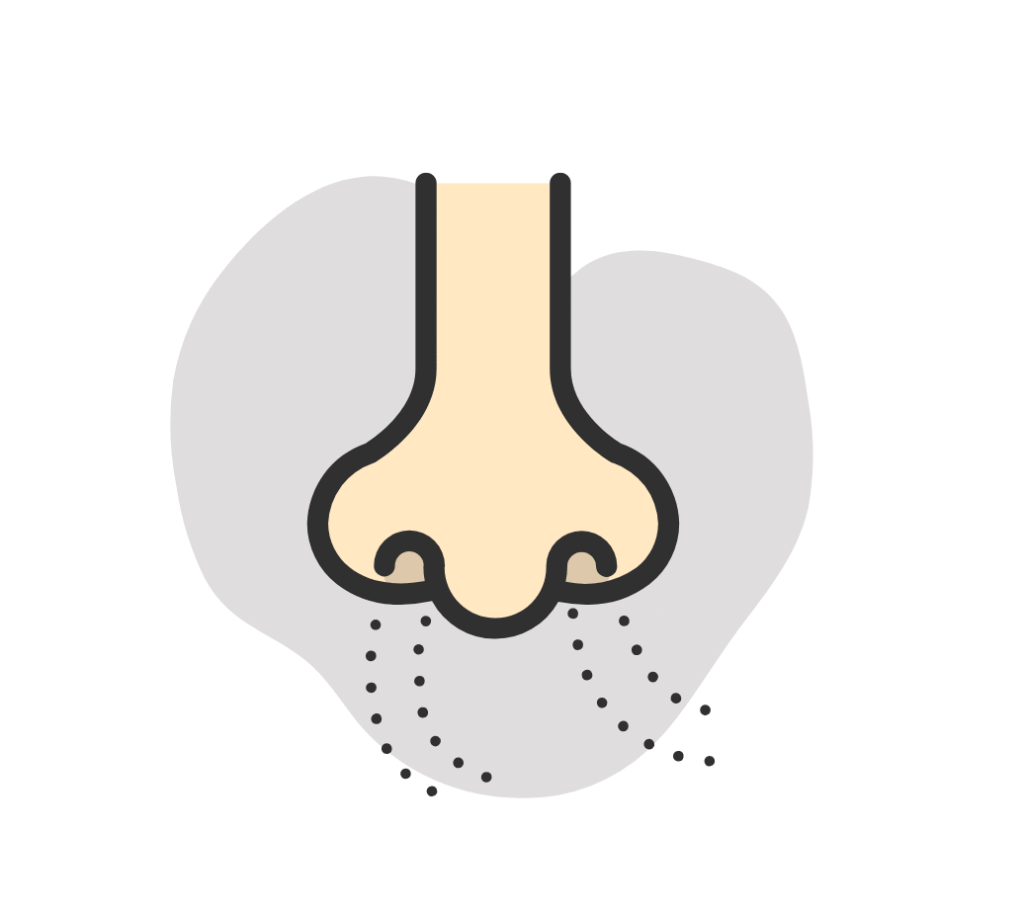
匂いを記録
字の通り、「匂い」の変化を記録する
◎得意
:尿の匂い、便の匂い、口臭の変化、耳の匂いなど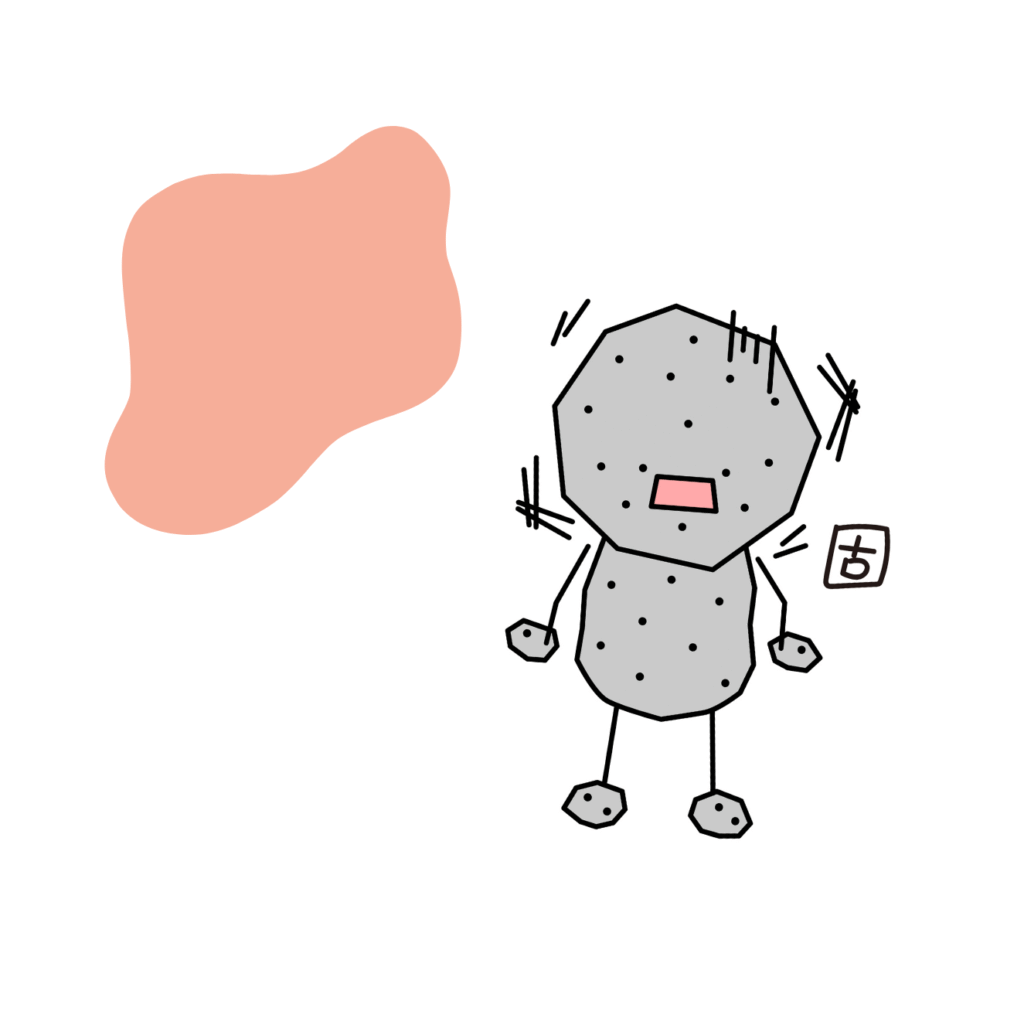
性質や形状を記録
形や色、物の柔らかさや粘度などを記録するのに適している
◎得意
:便の色や形、尿の色や含有物、嘔吐物、目ヤニや鼻水の色や粘り気など、食べているものの種類(ドライ/ウェット、粒のまま/ふやかしなど)
(余裕があれば、ベッドや床の素材など動物が使用しているものも記録してみましょう)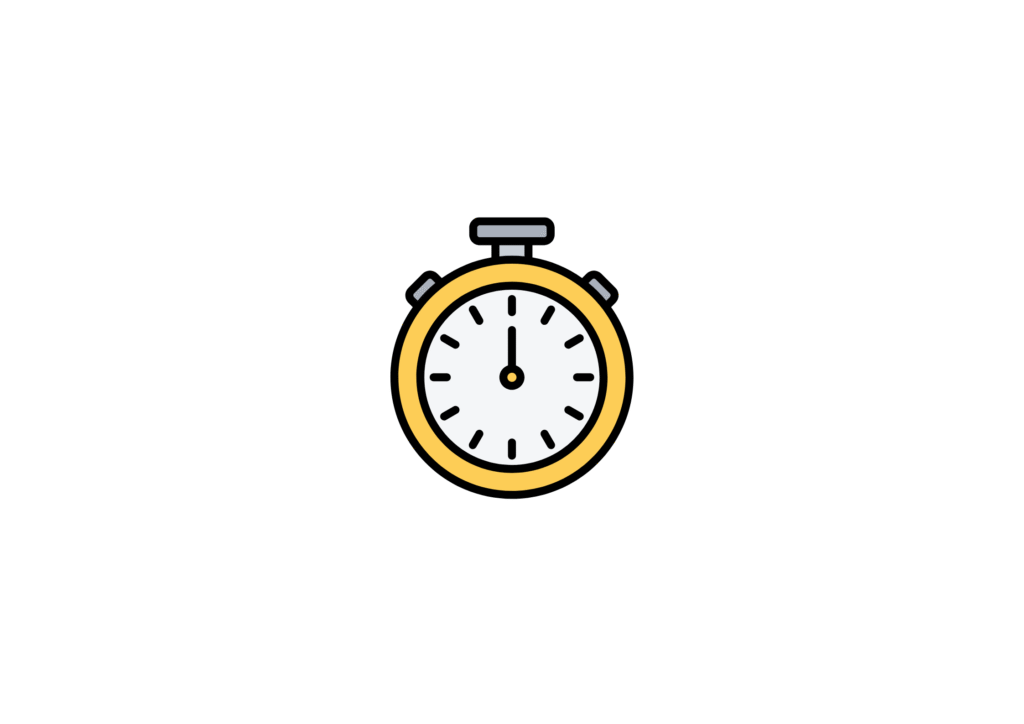
時間や様子を記録
行動や物事が起こったタイミングや続いた時間、連続して起こる状態の変化、解釈や表現の難しい様子の記録に適している
◎得意
:発作(タイミングや発作の時の様子)、嘔吐(タイミングやその後の様子など)
意図のわからない吠え、怪我や破行、咳やくしゃみ、呼吸の変化など動画や写真を上手に活用しよう!
写真や動画は非常に有益な情報になります。
特に性質や形状・動物の状態などは人によって解釈や表現に違いが出ることもあり、診察時のミスリードに繋がることもあるため、画像で見せてもらうことで正確な情報共有ができます。
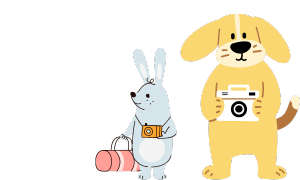
写真や動画は記録忘れを防ぎ、後から見返すことができるだけでなく、撮影時の日時なども遡って確認できるため、ひとまず撮影しておいて損はないでしょう。
記録する時に注目すべきポイント
以下は、人が観察しやすく(変化がわかりやすく)多くの疾患に関連のある項目で、入院管理などでも獣医師や動物看護師が欠かさずにチェックしている項目です。
ご自宅で健康チェックをする際にも、ぜひ意識して観察してみてください。
各項目の詳しい説明はこちらの記事をチェック(現在準備中)
食事
- 与えている内容
:どのメーカーのなんという名前の製品か把握しておきましょう - 与えている量
:正確なグラム数がわかるよう、計ってあげるを習慣に! - 与え方
:ドライのまま/ふやかして/ウェットと混ぜて など - 食事の環境
:使用している器の種類や形状、器の高さや床材、他動物との距離感など - おやつ
:あげている種類や量を確認しましょう
排泄物(尿)
- 色
:黄色尿、血尿、水っぽい(黄色よりも透明に近い)尿など - 匂い
:ツンとした匂い、生臭い匂いなど
”どんな” 匂いか説明が難しい場合は、いつもに比べて匂いが強い/弱いなどを観察しよう - 内容物
:キラキラ光っているものがある、ねっとりとしたものがあるなど - 量
- 回数(※24時間以上排泄が見られない場合は命に関わる場合がありますのですぐに病院に連れていきましょう)
- 排尿姿勢
- 排泄の失敗 など
排泄物(便)
- 色
:茶色、黄土色、緑っぽい色、血便、黒色便など - 匂い
:匂いの強さ種類など - 固さ
:軟便、泥状の便、水溶便、もしくはカチカチの便など - 量
- 回数(※2日以上排便がない場合はすぐに病院に連れていきましょう)
- 排便姿勢
嘔吐物
- 頻度
:月に1回/週に1回/1日複数回 など - タイミング
:食べてすぐ/30分以上経ってから/朝一/夜中 など - 嘔吐物
:液状/フード/フード以外/血混じり
フードの形(ふやけて形が崩れている/フードの形はそのままなど)など - 嘔吐後の様子
:いつも通りの元気がある/ぐったりしている/えずいている など
※嘔吐後いつも通りの元気がない場合は様子を見ずに病院に連れて行きましょう
行動や様子
- 活動量
- 体の動かし方
- 物事への反応(鈍い/過敏など)
- 意識の程度
- 呼吸の速さや深さ など
まとめ
いかがでしょうか?
こうして並べてみるとチェック項目が多く感じますが、まずは
◎健康なときの状態・様子をしっかりと把握しておくこと
そしてなにか異変があったときに
◎思い出せ、気づけるようにすること
そのための準備を日頃から少しずつしていくことが大切なのではないかと思います。
習慣になってしまえばなんてことない作業だと感じるはずです(^^)
まずはどれか一つ、意識して観察することから始めてみてはいかがでしょうか?