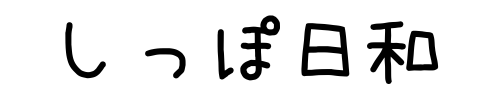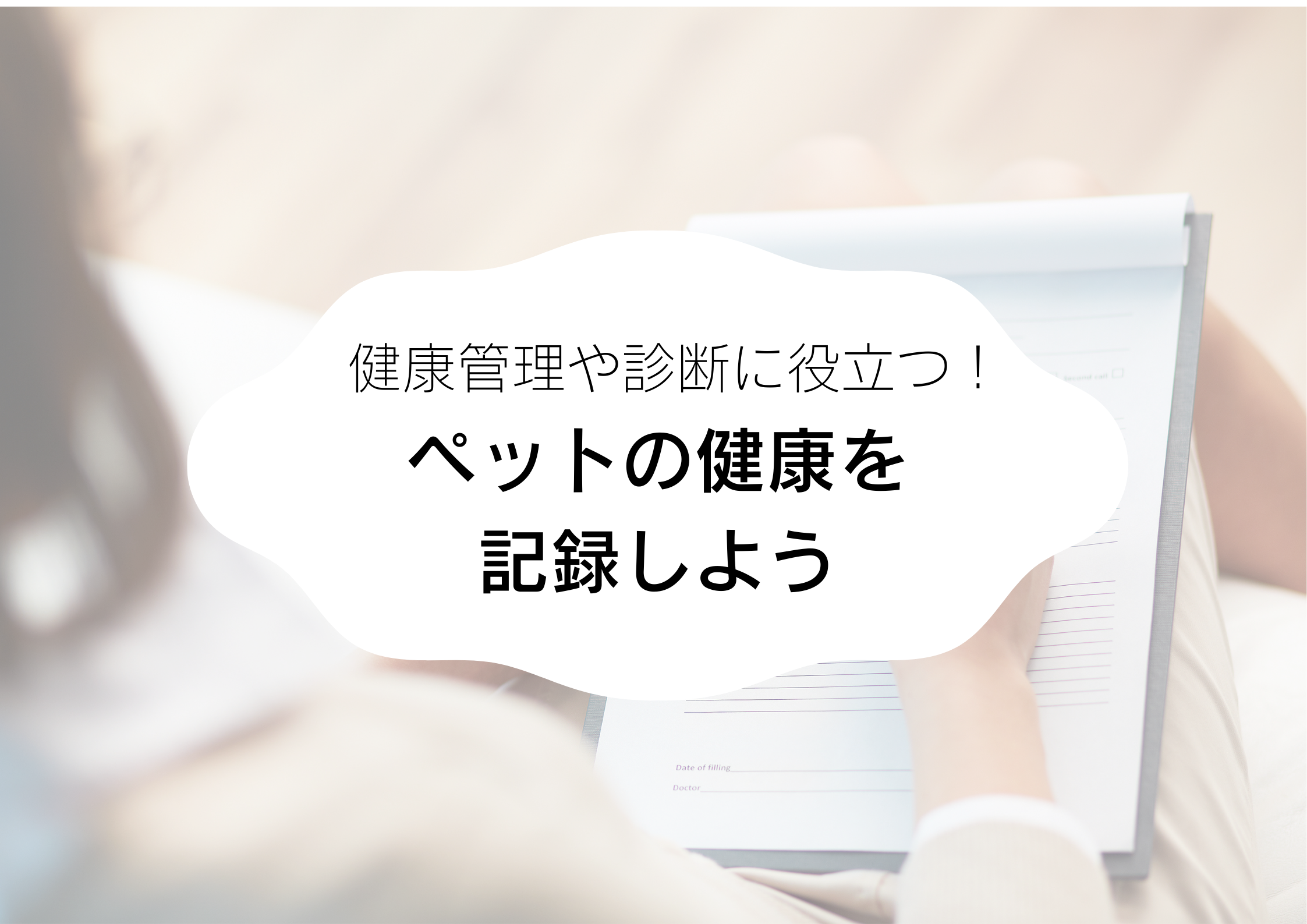前回の記事 【健康管理や診断に役立つ】ペットの健康を記録しよう では、
- どうして記録が必要なの?
- どんな方法があるの?
- どんなところに注目すればいいの?
についてお話ししました。
今回はその中のひとつ「食事」からみる健康管理についてさらに詳しく説明していきたいと思います。
前回の記事をまだチェックしていない方はこちらから⇩
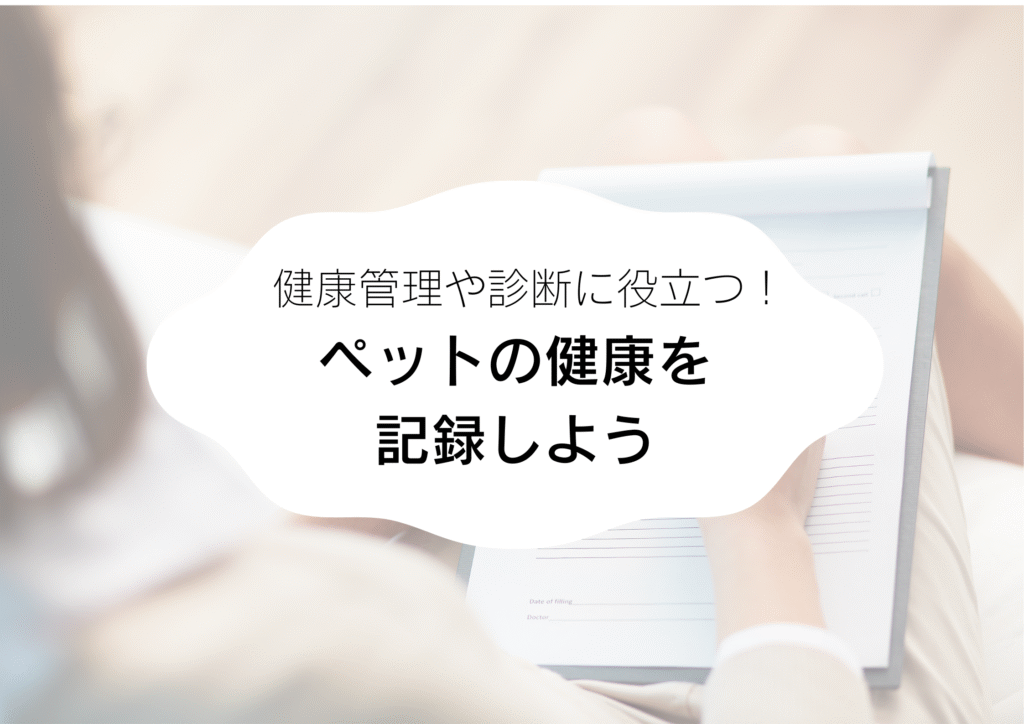
食事を観察するってどうゆうこと?
「食事のチェック」といわれると多くの方が 食欲が落ちていないかどうか = 食べる量が減っていないか に注目することが多いではないでしょうか?
食欲低下は多くの人が気づきやすい代表的な症状のひとつ。
- 消化器症状(下痢や便秘、吐き気など)
- 疼痛(骨折やヘルニアなど外科的なものから内科的な疾患まで)
- 重度の歯周病や口腔内腫瘍などの口腔内環境
- 心理的ストレス
などさまざまな身体的・精神的不調が「食欲低下」という形で現れます。
しかし、疾患の中には「食欲が増す」病気もあることはみなさんご存じでしょうか?
「食欲」ではなく「食べ方」や「食の好み」に変化が現れることもあります。
また、食べる量を確認する時は同時に “与えている量” にも注目しなければなりません。
このように、動物の不調は食欲低下以外にも現れることがあるため、「食欲の有無(食べる量)」を確認するだけではないということを頭にいれておきましょう。
では、動物の変化にいちはやく気づくにはどんなことに注目したらよいのでしょうか?
今回は食前・食事中・食後の3つのシーンに分けて、もう少し詳しく一つ一つのポイントについて説明していきます。
食前(準備中)のチェックポイント
与えているもの
動物のごはんは一般的にドライフード/半生フード/ウェットフード(/手作り食)があります(うさぎは除く)。
またパピーやシニア、尿路ケアや毛玉ケアなど特定の目的に合わせた食事でも分けられますね。
これらはその製品によってカロリー ・ 栄養素 ・ 原材料 ・ 水分量 ・ 食感 ・ 日持ち などが変わってきます。
- 同じ量をあげていても太る/痩せる
- 飲水量が減る/増える
- うんちの量が増える/減る 匂いや色、柔らかさが変わる
- おしっこの量が増える/減る
- 消化不良やアレルギー反応を起こす
- 動物の食の好みに合わない場合は食欲や食べるスピードが低下したり、食事に対する反応が鈍くなることがある
- ドライフードを食べなくなり、ウェットフードを好むようになった
などの変化は病気の症状のひとつのこともあれば、
食事(特にごはんを切り替えた時)そのものが影響している場合も考えられます。
病気の影響なのか?
食事の影響なのか?
その症状がどうして現れたのかを紐解く手がかりを得るため、
「何を食べているか」は診断と治療に大きな影響を与えるのです。
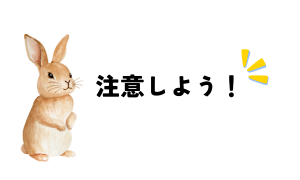
◎製品を変える際は
「いつから・どのように変えたか」を記録しましょう。
例)3日前に、全量パッと切り替えた
1週間前から、前の食事と混ぜながら切り替えた など
◎お家によっては”ごはんは〇〇の担当”など特定の人だけが把握している場合もありますので、ご家族みんなで共有しておきましょう。
食事の量
食事の量をチェックするときは必ず「与えている量」と「食べた量」を把握しましょう。
これらは主に
- 体重の増減は適切か
- 必要な摂取カロリーが摂れる健康状態であるか
この2点のバロメーターになります。
1、体重の増減は適切か?
体重変化の原因は過食や給餌不足〜病気までさまざま。
○適切な量を与えている(もしくは変えていない)のにどんどん痩せてしまう/太ってしまう
○実は知らないうちにあげすぎていた
○与えている量は適切なのに痩せない
○以前のようにごはんをバクバク食べない、残すことがある
このように「与えている量」に対して動物の体重や肉付きの変化をチェックすることで、
異常な変化(病気の可能性)なのか適切な変化なのかを見極めます。
2、必要な摂取カロリーが摂れる健康状態か?
○下痢でお腹が痛くて食べれなかったけど、昨日・今日と食べる量が増えている(回復の兆し)
○このお薬を投与しているけど、食欲が戻ってこない(薬の変更を検討?)
○いつもは○g食べているのに今日は○gしか食べなかった(不調の兆候かも)など「与えている量」に対して「食べた量(残した量)」を把握することで、
・治療中であれば回復度や治療方針の適切さを
・健康/ある状態を維持したい動物は体調の不調(変化)を
判断する手がかりになります。
与え方
与え方は、特に食事量(体重の変化)や食事のモチベーションに大きく影響を与えます。
「ごはんの工夫」と「環境の工夫」に分けて考えてみましょう。
<ごはんの工夫>
*ごはんについて*
○ドライフードのみであげている/ウェットフードと混ぜてあげている
○ドライフードをお湯でふやかしてあげている
○トッピングをする/しない
*与え方について*
○お皿であげている
○知育玩具を使用したり遊びながらあげている<環境の工夫>
*食事の環境について*
○他の同居動物の近く/違う部屋で食べている
○リビングで食べる/静かな場所で食べる
○床で食べる/高いところ(キャットタワーの上など)で食べる/台に置いて食べる
○いつも決まっている/毎日違うところ など*器について*
○陶器/プラスチック/銀皿
○平たいお皿/丸いお皿/深いお皿/傾斜のあるお皿
○背の低いお皿/高いお皿 など*足場について*
フローリング/カーペット/滑り止めマット など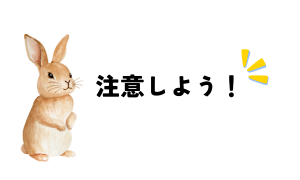
実は食べ物以外が食欲に影響していることも多い!
特にシニアや多頭飼育の猫などで食が不安定な場合は
食事環境をよ〜く観察して見直してみるとヒントが得られるかも?
食事中のチェックポイント
食事への反応
ごはんを用意したときにどのような反応をするかでも、動物の健康状態を予測することができます。
○全く見向きもしない
◯匂いを嗅ぎにくるけど、食べずに行ってしまう
○お皿の前で立ち止まる1、2口食べて去ってしまう
○いつもより反応が鈍い(飛んでこない)
○飛んでくるようになった/完食してもまだ欲しがる単に食事の好みや、たくさん遊んで疲れたなどの理由から、体の痛みやだるさ・吐き気などの不調が原因で反応が変わることもあります。
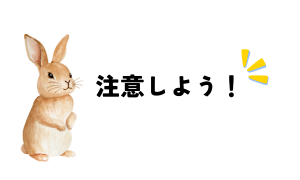
特に、ごはんやおやつの種類・量を変えていないのに
これらの変化が見られた場合は病気の可能性が考えられます
早めに受診しましょう
食事の食べ方
食事の食べ方は特にお口の状態(できものの有無や歯周病の進行度)を、
食べる時の姿勢は筋力の低下や足腰の不調などを把握するときなどに役に立ちます。
○噛んで食べるようになった/噛まずに食べるようになった
○顔を傾けて食べることがある
○口にひっかかるようなそぶりをすることがある
○立って食べるようになった(座るのがしんどい)
座って食べるようになった(立ってるのがしんどい)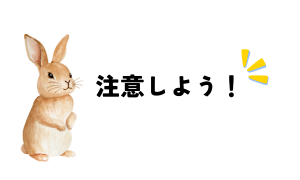
食べ方の変化は説明が難しく
動物病院で実際に見せることが難しい。
気になる様子が見られた場合は動画に残し
早めに受診しましょう
食事にかかる時間
食事にかかる時間は
「噛むときの痛みや違和感」「飲み込む時の痛みや違和感」「食事をする筋力や体力の低下」などの身体的(疾患的)な影響と
「他の同居犬や音が気になる」「安心した場所で食べれない」「遊び不足」などの心理的な影響が考えられます。
○噛む時間が長くなった/短くなった
○飲み込むときに喉に引っかかるような様子がある
○食べ続けられる時間が短くなった
○休憩しながら食べる食の好み
食の好みには「匂い」「味」「食感」「大きさ」などの影響が考えられます。
人が子供時代と大人になってから味覚や好みが自然と変わるように、必ずしも病気と関連があるわけではありませんが、病気と連動する場合もあります。
- 腎臓病(特にアダルト〜シニア期)
- 歯周病
- 口腔内腫瘤や食道腫瘤
- 顔面麻痺などの神経疾患
- 老化による顎の筋肉などの低下
などの可能性もあげられますので、食の好みの変化+その他の変化と合わせて観察し、気になる状態が続くようであれば受診をおすすめします。
食後の変化
嘔吐の有無
食後に嘔吐が見られた場合は、
「何を」「どれくらい経ってから」吐いたかをしっかり記録しておきましょう
「食後30分以内に吐いた」と言われれば誤食の可能性も考えなくてはいけないし、
「食後3時間後に吐いた」なら誤食の可能性は低いと考えるかもしれません。
「食後3時間経って吐いたのにドライフードの形が変わっていない」であれば消化機能の異常が疑われるように
嘔吐物と嘔吐のタイミングはとても大きな判断材料になります。
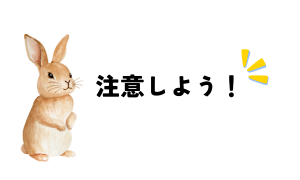
吐いた後ケロッとして続かないようであれば
緊急性は低いと考えられますが、
続けざまに吐く、週に何度も吐く、吐いた後にぐったりしている
などが見られた場合はなるべく早く病院に連れて行きましょう
毛づくろい
特に猫の場合、食後には毛づくろいが付きものですよね。
- 口の痛み
- 関節炎などの体の痛み
などがあると毛づくろいをしなくなることがあるため、食後に限らずよく観察しましょう。
毛づくろいが減ると
- 毛の艶がなくなる
- 換毛が増える
- 毛のもつれが増える
- 毛玉を吐く回数が減る
などの変化が見られることがありますので注意深く観察しましょう。
まとめ
今回は「食事からみる健康チェック」のポイントをお伝えしました。
長くなってしまいましたが、それだけ人が気づけるサインがたくさんあるということでもあります。
毎日の健康チェックは食事から!
「食欲低下」以外のヒントも取りこぼさないように日頃から「観察の目」を鍛えていきましょう!