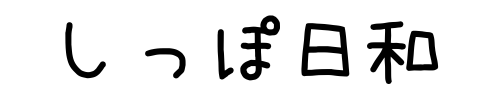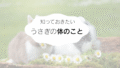ー動物との暮らしー
それはとても尊く価値のあるもので、同時にとても大変で重い責任が伴うもの。

屋外飼育から室内飼育へ。
残飯からバランスの整った総合栄養食や手作りフードへ。
ワクチン接種率の増加や医療技術の向上により平均寿命が伸び、皮膚科や歯科など専門病院も増え、高度な医療技術が受けられるようになった現代。

番犬や害獣対策として飼われていた時代から、「家族」の一員になった動物たち。
ここ数十年で動物と人の関係は大きく変わり、
我が子のように
孫のように
時には親友のように
あるいは相棒のように
動物たちはかけがえのない存在に変化していきました。
人に癒しを、喜びを、愛しさを、時には苦しみを教えてくれる尊い動物たちを、私たちはどうやって幸せにしてあげられるだろう?
良質な食事を提供する、動物病院に連れて行く、お散歩に連れて行く、時にはファッションや旅行を一緒に楽しんだりする、もしくは人間社会で困らないようにルールを教える(いわゆるしつけ)
動物と幸せな生活を送るためにしていることがたくさんあると思います。
一方で、動物は人とは全く違う生き物であることも忘れてはいけません。人の好意が時には迷惑になったり、人の行動が動物に脅威や恐怖を与えてしまうこともあります。また生物学的な体の構造上、人と同じように接してしまうと健康を害したりケガをさせてしまうなんてこともあるでしょう。
犬や猫、うさぎといった動物種を尊重しながら人と幸せ暮らすためには適切な知識が欠かせません。

今回はそんな動物の「幸せ」を動物福祉の観点から考えていきたいと思います。
少し長くなりますが、ぜひご一読ください♪
動物福祉と動物愛護
「動物福祉」と「動物愛護」
よく耳にする言葉ですが、この2つの持つ意味は似ているようで同じではありません。
動物愛護という概念はもともと畜産動物に対する虐待を取り締まるために生まれたもので、動物に対する思想の発展に伴い、イギリスの家畜福祉協議会(FAWC)が初めて提唱したのが動物福祉の5つの自由です。
当初は畜産動物に限られていましたが、現在では実験動物や展示動物、伴侶動物といったあらゆる動物に適用されるべき理念として世界獣医学協会(WVA)などでも取り入れられています。
では、動物愛護と動物福祉にはどのような違いがあるのでしょうか?
動物愛護とは
…”動物を愛し、護る”こと。命の尊厳を守り、みだりに虐待されたり、不当な苦痛を与えられないように護ること。
簡単に言うと、”可愛がり、大切に扱う”という人間の感情そのものを指すこと。
例)人間の都合で殺処分することを反対する
動物福祉とは
…家畜や実験動物、伴侶動物などその種類にかかわらず、人間の管理下におかれる全ての動物が肉体的・精神的に最大限苦痛なくより幸福でいられる状態を、客観的事実に基づいて目指すこと。
例)なんらかの理由で殺処分を余儀なくされた時、二酸化炭素ガスによる窒息死で恐怖と苦しみになか命を奪うのではなく、麻酔で意識や感覚を消失し、痛みや恐怖を感じなくさせたあとに薬物を投与し、苦しまないように眠りにつかせる
日本でもペットに限らず、水族館や動物園などでも多様なエンリッチメントを取り入れて動物福祉を向上させる動きが高まっています。
動物福祉の「5つの自由(Five Freedom)」
動物福祉の「5つの自由」 = 動物が心身ともに健康に生きるため守るべき最低限の条件。
ここで重要なのは、「心身」の健康
つまり、体の健康だけではなく「心」の健康も大事であるという点です。
でも、人と全く違う生き物にとっては何が幸せなの?
”人と違う”というところが、難しくもあり、何ものにも替えられない魅力でもありますよね。
そこで役に立つのが動物福祉の「5つの自由」です。
5つの自由は、動物の幸せを考えるときの「道標」のようなもの。
この子にとって幸せってなんだっけ?と迷子になってしまったときは、この5原則を見つめ直してみると、ヒントを得られるかもしれません。
前置きが長くなりましたが…^^;
さっそくその5つの自由とはなんなのか、その中身を詳しく見ていきましょう!
〜動物福祉の5つの自由(Five Freedom)〜
ⅰ.飢え・渇きからの自由
ⅱ.不快からの自由
ⅲ.痛み、怪我、病気からの自由
ⅳ.恐怖・不安からの自由
ⅴ.本来の動物らしい行動が取れる自由
飢え・渇きからの自由
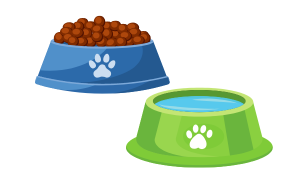
- 健康を維持するためにバランスの取れた食事を十分に与えられ、食べることができる
- 新鮮な水をいつでも飲める
例えば、パピーとシニアでは活動量や代謝の違いから必要なエネルギー量や栄養素が異なるため、その動物のライフステージに適した食事を与えなければならないし、
疾患がある場合は特定の栄養素の摂取を抑制したり補填する必要もあるため、適切な食事が治療の一環にも繋がります。
介護期などは飲み込む力が弱まったり自分で体を支えることができないこともあるため、ごはんの形状を工夫したり、食べやすい体勢を維持できるように介助するだけで、食事に対するモチベーションが上がり食欲が増えることもあります。(※老齢期〜介護期の食事の変化についての記事は現在準備中です)
また、十分にお水を飲むことは腎臓病や歯周病などの予防にもつながります。
「与える」だけでなく、動物がどうやって「体に取り入れるか」まで考えてあげると、更なるQOLの向上につながるのではないでしょうか?
不快からの自由
- 自分の意志で自由に立つ・座る・横になることができ、体の向きを変えられる十分なスペースがある
- 生活環境は常に清潔に保たれ、安心して気持ちよく休むことができる
- 雨風や強い日差しから身を守ることができる、空調管理がされている など

動物先進国といわれる欧米諸国一部のシェルターでは、動物種に合わせて部屋の大きさや高さが義務付けられているほど、動物が自分の意志で自由に動き回れることは動物福祉において重要なことだと考えられています。
動物種によって必要な環境は異なるため、迎え入れる前にその動物がどんな習性を持っているのかを学んでおくことが重要です。
また多くの動物は、その動物種特有の習性が排泄場所や寝食の場所に影響します。
時には人が用意する生活環境に不快感を示すこともあり、排泄を我慢して膀胱炎を引き起こしたり、排泄の失敗や食糞などのトラブルに繋がることもあるため、気になる行動がある場合は居住スペースを見直すことも改善のヒントになるかもしれません。(※心地よい生活環境に関する記事は現在準備中です)
痛み、怪我、病気からの自由
- 病気や怪我の危険がある環境下で飼育しない
(炎天下の散歩、滑りやすい床、落下の危険のあるソファなど) - 継続的な健康管理(ワクチン接種や健康診断など)
- 病気や怪我をしたときは適切な医療を迅速に受けることができる
ここで看護師としてお伝えしたいポイントがひとつ!

重症度に限らず、おかしいな?と思ったらできるだけ早く病院に連れて行きましょう。
多くの場合「様子をみよう」に良いことはありません!
早期治療は命の危険を防げるだけでなく、治療にかかる期間や治療時に生じる痛みの強さを減らすことにもつながります。
病院で痛い思いをすればするほど診療時の動物の精神的ストレスも大きくなり、
また治療にかかる金額や手間なども増えるため人にとっても良いことはほぼないでしょう。
”こんなことで行ったら迷惑かも…”なんてことは考えず、動物のことを最優先に考えましょう。
病院のスタッフも快く受け入れてくれるはずです(^^)
また病気や怪我をしない健康管理・環境づくりもとても大切です。こちらについてはまた別の記事でお話しします(※現在準備中)
恐怖・不安からの自由
- 恐怖や不安などの精神的苦痛から守り、原因を取り除く。
もしくは原因による心理的ストレスを可能な限り軽減するよう努める。
動物が恐怖や不安を感じる原因は様々です。痛みの場合もあれば、対犬関係や対人関係、育ってきた環境やもともとの気質・体格や動物種・特定のシチュエーションなどが大きく影響することもあるでしょう。

また、ブルブル震える・体を縮こまらせて固まる・攻撃するなどわかりやすい表現もあればお腹を出す、しっぽを振る、人を舐めるなどシチュエーションによっては親愛表現の意味も同時に持つ行動をする場合もあります。
ごはんの食いつきが悪いや排泄のタイミングがずれる、寝ている時間が増えたり人のあとをついて回るなど、日常的な行動であるものの、その頻度や量に変化が現れることもあるでしょう。
まずは、動物が「恐怖や不安を感じている」ことに気づくこと。そのために、
- いつもの様子をよく観察しておく
- その動物種特有のボディーランゲージや習性を学ぶ
ことから初めてみることをおすすめします。
解決に向けてどうすればわからない場合は自分で頑張りすぎずに、ぜひトレーナーや行動分析学に精通した専門家に相談してみてくださいね。
本来の動物らしい行動がとれる自由
- その動物種が持つ本来の生態や習性に基づいた行動を自由に行えること
- 人間社会に適応させようとするがあまり動物の行動を抑制しない
たとえば、伸び続ける歯を持つうさぎ。
うさぎはその歯の特性から、「噛む」という行動がよく出る動物です。カーテン、ソファ、コード、洋服、、、かくゆう投稿主も、なんど洋服に穴を開けられたことか…(とほほ涙)
ですが、だからといってコラ!と叱ることは正しいのでしょうか?
もともとうさぎはそういう生き物。しかも、その生き物を人間社会に引き入れたのは我々人間であり、お迎えすると決めたのは自分自身です。
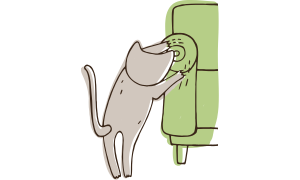
人が困るからやらせない、はあまりに横暴ですよね。
洋服は噛まれたら困るから、洗濯物がある部屋はいけないように柵をしておこう。
その代わり噛んでも良い牧草やおもちゃをあげるね。
と考えられれば、うさぎの習性を守りながら人の悩みも解決するのではないでしょうか?
犬のお散歩中の排泄やにおい嗅ぎ行動猫の爪とぎ問題など動物種によって習性はさまざま

どうしてその行動をするのかな?
代わりに何をさせてあげられたら動物は満足するかな?
どちらか一方に合わせるのではなく、人も動物も受け入れることができる中間地点を探して行くことが、お互いが気持ちよく過ごせる解決策になるのではないでしょうか?
まとめ
「動物福祉の5つの自由」はいかがでしたでしょうか?
人が地域によって文化や言語が変わるように、動物も種によって生まれ持った生態や習性はさまざま。
同じ日本人でも趣味やライフスタイルが違うように、同じ動物でも個体によって性格や好みはそれぞれです。
その動物のことを一番理解できるのは、いつもそばで暮らしているご家族です。
これまでたくさんつらつらと書いてきましたが、、、
正解はひとつではなく、その正解を知っているのはあなたと動物だけ。
ぜひ動物とたくさん会話をして、昨日よりも今日、今日よりも明日が豊かで幸せな日になりますように